
「1年間の語学留学をしたいけれど、費用が心配…」
そんな悩みを持つ高校生・大学生・社会人に向けて、この記事では語学留学の費用を抑える具体的な方法を紹介します。
2025年最新の情報をもとに、安い国の選び方・滞在スタイル・節約術・助成制度まで幅広くカバー。
実例や体験談も交えながら、無理なく実現するためのリアルな選択肢をわかりやすく解説します。
「どうすれば行けるのか?」を真剣に考える人のための一歩踏み出すガイドです。
この記事のポイント:
- 語学留学費用は国・都市・滞在方法で大きく異なる
- 節約には自炊・ルームシェア・交通手段の工夫が効果的
- 奨学金やワーホリ制度を活用すれば予算内で実現できる
- 情報収集と計画次第で「行ける留学」は誰にでも見つかる
語学留学の費用を正しく理解するための基礎知識
- 留学費用の主な内訳と相場感
- 語学留学の国ごとの費用傾向
- 滞在形式と生活費の違い
- 語学学校の種類と料金の差
- エージェント利用の有無によるコスト差
- 留学前の準備費用とタイミング
留学費用の主な内訳と相場感

語学留学を検討し始めたとき、まず気になるのが「一体いくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。
実際のところ、語学留学の費用は国や滞在方法、生活スタイルによって大きく異なりますが、全体像を知っておくことで無理のない計画が立てられるようになります。
まずは、語学留学に必要な主な費用項目と、それぞれの目安金額を見てみましょう。
| 費用項目 | 内容 | おおよその金額(1年間) |
|---|---|---|
| 授業料 | 語学学校での授業にかかる費用(週15〜25時間程度) | 約50万〜150万円 |
| 滞在費 | ホームステイ、学生寮、シェアハウスなどの住居費用 | 約50万〜100万円 |
| 航空券代 | 渡航費(年1〜2回の往復便) | 約10万〜30万円 |
| 生活費 | 食費、交通費、日用品、通信費、交際費など | 約30万〜60万円 |
| 保険・ビザ関連費用 | 留学保険、学生ビザ、健康診断等 | 約5万〜20万円 |
こうした費用を合算すると、一般的な語学留学の年間コストは150万〜300万円前後が相場となります。
為替の影響も大きいため、通貨ごとの感覚を持っておくことも大切です。
2025年5月現在の参考為替レートは以下の通りです:
- 1米ドル ≒ 155円
- 1カナダドル ≒ 114円
- 1オーストラリアドル ≒ 102円
- 1ユーロ ≒ 167円
- 1フィリピンペソ ≒ 2.7円
たとえば、月10万円の家賃はカナダなら約870カナダドル、フィリピンなら約37,000ペソほどになります。
国によって、同じ額面でも体感コストがまったく違うことは念頭に置いておきたいポイントです。
また、初期費用としては入学金・手続き費用・初回の航空券・滞在先保証金などがかかるため、渡航前に30〜50万円程度のまとまった出費が想定されます。
費用を抑えるうえで大切なのは、「自分にとって譲れないものは何か」を明確にし、それ以外の部分でメリハリをつけること。
全体像を把握したうえで、次章からは実際にどの国や選択肢が“安く済む”のかを見ていきましょう。
語学留学の国ごとの費用傾向

語学留学の費用は、渡航先の国によって驚くほど差があります。
なぜなら、授業料や滞在費だけでなく、物価、為替レート、ビザの条件、現地での収入可否など、さまざまな要素が費用に影響を与えるからです。
ここでは、代表的な留学先である英語圏の5カ国を中心に、1年間の留学費用の目安を比較してみましょう。
| 国名 | 授業料(年間) | 滞在費(年間) | 合計目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン | 約50〜70万円 | 約30〜50万円 | 約80〜120万円 | 授業密度が高くコスパ最強。マンツーマン中心の集中型 |
| マルタ | 約60〜90万円 | 約40〜50万円 | 約100〜140万円 | 欧州の中では格安。歴史と観光のバランスが魅力 |
| カナダ | 約80〜130万円 | 約70〜100万円 | 約150〜230万円 | 教育水準が高く、都市によって費用に差あり |
| オーストラリア | 約100〜150万円 | 約80〜120万円 | 約180〜270万円 | 治安と自然が魅力。ワーホリ利用で学費の一部回収も可 |
| アメリカ | 約120〜180万円 | 約90〜130万円 | 約200〜300万円 | 留学王道だが物価高。ビザ制限も要確認 |
費用を大きく左右するのは、授業料と滞在費です。
たとえば、フィリピンでは月5万〜7万円で授業+寮生活が可能ですが、アメリカでは同じ条件で月20万円以上かかるケースもあります。
どの国に行くかによって、1年で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。
また、為替レートの影響も無視できません。
たとえば、カナダドル(約114円)やフィリピンペソ(約2.7円)に対して、ユーロ(約167円)や米ドル(約155円)は日本円ベースで割高に感じられるため、授業料や生活費の総額にも影響します。
さらに、国によっては就労ビザ(ワーキングホリデー)や学生ビザ中のアルバイトが許可されており、現地収入で一部費用を補うことも可能です。
「高い国=行けない」ではなく、「どうやって資金計画を組むか」がカギになります。
国選びは、「費用面」「教育内容」「生活環境」の3軸で冷静に比較するのが成功の秘訣です。
次は、滞在方法によって変わる生活コストについて見ていきましょう。
滞在形式と生活費の違い

語学留学において、どのような住まいを選ぶかは費用全体に大きな影響を与えます。
まずは、主要な3つの滞在スタイルを比較した表をご覧ください。
| 滞在形式 | 食事 | 費用(月額) | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ホームステイ | 2食付き(朝・夕) | 約8万〜12万円 | 現地文化に触れられる/英語実践の場が多い | 家庭との相性により快適度が変わる |
| 学生寮 | 施設による(食事なしが多い) | 約7万〜10万円 | 通学が便利/治安面で安心 | ルールが厳しい/騒音の懸念 |
| シェアハウス | 自炊 | 約5万〜9万円 | コストが安い/自立した生活ができる | 炊事・掃除がすべて自己責任 |
ホームステイは、現地の家庭で生活を共にするスタイルです。
英語を使う機会が自然と増え、文化に深く触れられる点が魅力ですが、一方で家庭ごとにルールやライフスタイルが異なるため、柔軟な対応力が求められます。
家庭との相性が快適さを大きく左右することもあります。
学生寮は、語学学校が管理する安全性の高い施設で、多くの場合キャンパスに併設されています。
通学のしやすさと防犯面での安心感は大きなメリットですが、門限や共有ルールが厳しかったり、騒音問題が起こることも。
住環境やルームメイトとの相性も重要です。
シェアハウスは、他の留学生や現地の若者と家を共有する形式で、最も自由度が高くコストを抑えやすい選択肢です。
節約重視で、自炊も苦にならない人には向いていますが、住まいの管理は自己責任。掃除や生活マナーの差でトラブルになるケースもあります。
さらに、どの形式を選ぶにしても「都市か地方か」で家賃相場は大きく変わります。
都市部を避けて郊外や地方都市に滞在するだけで、月2〜3万円の節約につながることもあります。
住環境は、快適さと節約の両立がカギ。自分の性格や生活スタイルに合った選択をすることが、満足度の高い留学生活への第一歩です。
語学学校の種類と料金の差
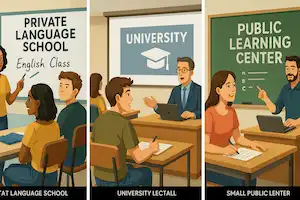
語学留学にかかる費用の中でも大きなウェイトを占めるのが、学校の授業料です。
しかし、語学学校にはいくつかの種類があり、その性質や料金設定に大きな違いがあります。まずは代表的なタイプを比較した表をご覧ください。
| 学校の種類 | 特徴 | 費用(週あたり) | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 私立語学学校 | 民間運営。選択肢が豊富で短期〜長期に柔軟対応 | 約2〜4万円 | 自分のペースで通いたい/集中して学びたい |
| 大学付属の語学コース | 現地大学が提供。進学目的の留学生が多い | 約3〜5万円 | 将来の進学を視野に入れている人 |
| 公立(地域運営)語学学校 | 一部国で提供。費用が安め/開講数は少なめ | 約1.5〜3万円 | できるだけ費用を抑えたい人 |
私立語学学校は、語学留学で最も一般的な選択肢です。
民間企業が運営しており、授業時間・開始日・期間の自由度が高いことが特徴です。
授業は会話中心の実践型が多く、国際色も豊か。料金は週2万〜4万円が相場で、1年通うと約80万〜150万円程度になることが多いです。
短期〜中期留学に人気ですが、費用はやや高めです。
大学付属の語学コースは、現地の大学が提供しているもので、将来的にその大学への進学を目指す留学生が多く在籍しています。
カリキュラムはアカデミック寄りで、授業の進度もややハイレベル。授業料はやや高めで、週3万〜5万円前後。
大学の施設が使えたり、学生との交流機会があるなど、「大学生活の予行演習」しての価値もあります。
公立語学学校は、カナダやニュージーランドなど一部の国で提供されている選択肢です。
自治体や教育委員会が運営しており、費用はかなり抑えめ。
ただし、私立校ほどの柔軟性やサポート体制は期待できず、入学時期が年2回など限定されることもあります。
費用優先であれば、検討の価値は十分にあります。
いずれの学校でも、「フルタイムコース(週20時間以上)」か「パートタイムコース(週15時間以下)」かで料金が変わります。
時間数が多いほど料金は上がりますが、学生ビザの取得条件に“フルタイム就学”が必要な国もあるため注意が必要です。
また、授業料には入学金・教材費・アクティビティ費用が含まれていない場合も多く、申込時に「最終見積り」を必ず確認しましょう。
後から「こんなにかかるとは思わなかった…」とならないためにも、総額ベースで費用を把握しておくことが重要です。
エージェント利用の有無によるコスト差

語学留学の情報収集を始めると、多くの人が最初に出会うのが「留学エージェント」の存在です。
エージェントは学校選びから申込手続き、ビザの取得サポート、滞在先の手配までを代行してくれる便利な存在ですが、当然ながらそこには費用が発生します。
| 項目 | エージェント利用あり | エージェント利用なし |
|---|---|---|
| サポート内容 | 手続き代行・学校紹介・生活サポートなど | すべて自己手配 |
| 手数料 | 無料〜20万円程度 | 原則ゼロ(自己負担のみ) |
| 利用者層 | 初めての留学/時間がない人/サポート重視 | 費用を抑えたい人/情報収集が得意な人 |
エージェント利用ありの場合、ほとんどの手続きがワンストップで完了するため、「留学の準備が不安」「忙しくて自力では難しい」という人にとっては安心感があります。
「無料エージェント」と謳われているサービスもありますが、実際には語学学校側に支払う授業料に仲介手数料が上乗せされているケースが多く、結果的に費用が高くなるという点には注意が必要です。
また、トラブル時の対応や緊急連絡先を提供してくれるエージェントもあり、不測の事態への備えを優先する人には適した選択肢です。
一方で、エージェントを使わずに自力で手配する方法も、費用を抑える手段として有効です。学校の公式サイトから直接申し込めば、中間手数料を省略でき、数万円〜十数万円の節約につながることもあります。
最近では「現地エージェント」や「オンラインサポート」のような選択肢も増えています。たとえば、学校は自分で選びつつ、申込部分だけサポートしてもらうなど、サポートの部分的な活用が可能になってきています。
結局のところ、重要なのは「自分にとって何が必要かを明確にすること」です。
たとえば以下のような観点で、自分の優先順位を整理してみましょう:
英語での申込や学校とのやりとりに自信があるか?
時間や手間をかけて調べることに抵抗はないか?
トラブル発生時に自力で対応できる情報力・語学力があるか?
安心感とサポートを“お金で買う”ことに納得できるか?
このような自己診断を通して、エージェントに「任せたいのか」「部分的に使いたいのか」「完全に自力でやりたいのか」が見えてきます。
金額だけで判断するのではなく、必要な安心やサポートの度合いを見極めたうえで、選択肢を比較することが大切です。
留学前の準備費用とタイミング

語学留学にかかるお金は、現地での生活費や授業料だけではありません。
実は出発前にもまとまった費用が発生します。
準備段階での支出を見落としていると、「想定より初期費用がかかった…」という事態にもなりかねません。
まずは、出発前に必要な費用の目安を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 | 目安金額 |
|---|---|---|
| パスポート・ビザ取得費 | 新規申請・更新・学生ビザ申請料 | 約2〜5万円 |
| 海外留学保険 | 医療・盗難・賠償補償など | 約10〜25万円/年 |
| 航空券 | 往復または片道(繁忙期で変動) | 約10〜25万円 |
| 入学金・登録料 | 語学学校に支払う初期費用 | 約1〜3万円 |
| 最初の授業料・滞在費 | 1〜3か月分を前払い | 約30〜60万円 |
| 生活用品・両替・SIM準備など | 日用品・初期通信環境整備 | 約2〜5万円 |
こうして見ると、出発前の準備費用だけでも合計で50万〜100万円程度が必要になるケースが多いことが分かります。
中でも大きいのは「授業料と滞在費の前払い分」と「海外留学保険」です。
特に保険はビザ申請の条件になる国もあるため、削れない出費と考えておきましょう。
保険料を抑えたい人は、安い留学保険プランの選び方や1年分の費用相場をあらかじめチェックしておくのがおすすめです。
👉 海外留学保険の選び方:1年分の費用目安と安いプランを見つける方法
また、出発時期によって航空券の価格は大きく変動します。
夏休み・春休みなどの繁忙期を避けるだけで、片道5万円以上節約できることもあります。
さらに、留学準備には意外と「時間」も必要です。以下はおおまかなスケジュール感です:
出発の6か月前:行き先・学校選定、エージェント選び
3〜4か月前:ビザ申請、保険・航空券手配
1〜2か月前:授業料支払い、荷物準備
直前:現地との連絡・持ち物最終確認・SIMや両替
このように、「お金」だけでなく「段取りと時間」も余裕を持って準備することが、スムーズな渡航とコストの最適化につながります。
計画的に準備を始めれば、費用を抑えるチャンスも多く見つかります。
留学オプション別の費用比較と節約の実践方法
- 組み合わせで変わる1年間の費用モデル
- コスパ重視で選ばれる人気国と理由
- 現地での節約アイデアと生活の工夫
- 働ける留学(ワーホリ・インターン)の活用法
- 奨学金・助成制度の活用ステップ
- 実例紹介:節約留学を成功させた人の工夫
組み合わせで変わる1年間の費用モデル

語学留学の費用は、「どこの国へ行くか」だけではなく、どんなスタイルで留学するかの組み合わせによって大きく変動します。
国、学校の種類、滞在方法、生活スタイルをどう組み合わせるかで、年間で数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。
以下は、目的や価値観ごとに代表的な4つのパターンを整理し、それぞれの費用感や特徴を比較したモデルです。
| モデル | 国・学校・滞在形式の例 | 年間の費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| コスパ重視型 | フィリピン × 私立語学学校 × 寮 | 約90〜120万円 | 授業密度が高く、生活費込みで最安水準 |
| 手頃な欧州型 | マルタ × 私立語学学校 × シェアハウス | 約100〜140万円 | ヨーロッパで費用が抑えられ、観光も楽しめる |
| バランス型 | カナダ/オーストラリア/NZ × 私立語学学校 × ホームステイ | 約150〜200万円 | 教育・治安・就労条件のバランスが良く安心感あり |
| 教育充実型 | アメリカ/イギリス × 大学付属語学コース × 学生寮 | 約220〜300万円 | 進学志向やアカデミック志向に最適、費用は高め |
コスパ重視型は、フィリピンやマレーシアなどの物価が安い国を選び、寮滞在とマンツーマン授業がセットになった語学学校を利用するスタイルです。
1年通っても100万円前後に収まるケースも多く、短期集中・初級者に特に人気があります。
手頃な欧州型は、近年注目度が上がっているマルタが代表例です。
ヨーロッパの中では圧倒的にコストが安く、美しい街並みや地中海の気候を楽しみながら英語を学べるのが魅力です。
滞在はシェアハウスが一般的で、生活費も比較的抑えられます。
バランス型は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランドといった「教育水準・治安・生活環境・就労可」のバランスが取れた国が該当します。
私立語学学校+ホームステイの組み合わせが定番で、語学+現地生活+ワーホリの可能性を兼ね備えた選択肢です。
教育充実型は、アメリカやイギリスの大学付属語学コースを選び、学生寮で生活するスタイル。
アカデミックな授業内容が中心で、大学進学や本格的な英語力習得を目指す人に向いています。
その分、費用は高額になりますが、教育の質や設備面では高い満足度が得られる傾向があります。
このように、留学費用は単に国の違いだけではなく、「国 × 学校タイプ × 滞在スタイル」の掛け合わせで大きく変わります。
まずは自分の優先順位(費用、生活環境、将来の進路など)を明確にしてから、どのモデルが自分に合うかを見極めていくのが成功のカギです。
コスパ重視で選ばれる人気国と理由

語学留学の費用を抑えたいと考える人にとって、どの国を選ぶかは非常に重要なポイントです。
物価、授業料、滞在費、ビザの条件など、国ごとの特徴を踏まえることで、予算内に収まる選択肢を見つけやすくなります。
以下は、「安くて学びやすい」として定評のある4カ国を取り上げ、それぞれの都市ごとのコスト感と特徴を紹介します。
フィリピン:都市別に選べる圧倒的コスパと集中環境
授業密度と費用のバランスを考えると、今なお最強といわれるのがフィリピンです。
私立語学学校では、1日4〜6時間のマンツーマン授業が標準。短期間での英語力アップを目指す人に人気です。
都市ごとに費用や学習環境が異なり、次のような傾向があります:
| 都市 | 特徴 | 月額費用の目安(授業+寮+食費) |
|---|---|---|
| セブ | 学校数が多く、リゾート感あり。価格は平均的 | 約8〜12万円 |
| バギオ | 山間部で涼しく、真面目な学習環境が整う | 約7〜10万円 |
| マニラ | 首都で利便性は高いが、やや高コスト | 約10〜14万円 |
学校は寮と食事込みのパッケージが一般的で、年間でも90万〜120万円程度に抑えられることが多く見られます。
自炊不要、通学不要で効率的な生活ができるのも大きな魅力です。
マレーシア:都市型ライフと物価の安さが両立
英語が準公用語として使われているマレーシアも、コスパ重視の留学先として注目されています。
中でも、都市ごとに雰囲気と費用感が異なるのが特徴です。
| 都市 | 特徴 | 月額費用の目安(授業+滞在費) |
|---|---|---|
| クアラルンプール | 首都。語学学校が多く、インフラも整う | 約10〜13万円 |
| ペナン | 穏やかな雰囲気で治安が良く、自然も豊か | 約9〜12万円 |
| ジョホールバル | シンガポール国境に近く、週末観光も可能 | 約10〜12万円 |
授業スタイルはグループ中心ですが、現地の大学キャンパスに併設された語学センターなどもあり、生活環境の安定度と費用バランスの良さが魅力です。
年間では100万〜140万円前後で抑えられるケースが多く、都市生活と節約を両立したい人にぴったりです。
マルタ:ヨーロッパで唯一の「手頃な英語圏」
ヨーロッパの美しい地中海に浮かぶ小国マルタは、英語が公用語でありながら、費用が非常に抑えやすい点で注目されています。
EU圏からの留学生が多く、国際色が豊かで、観光も楽しめる点が魅力です。
授業料+生活費で月10万〜13万円が平均的
年間で100万〜140万円ほどに収まる
シェアハウス滞在が主流で、生活費を自分でコントロール可能
ヨーロッパ文化を味わいつつコストも抑えたい人には、理想的な選択肢といえます。
ニュージーランド:都市によって選べる学びと暮らし
自然豊かで穏やかな国民性が魅力のニュージーランドも、近年人気を集めているコスパ国のひとつです。
学生ビザでも週20時間までのアルバイトが可能なため、現地収入を得ながら生活費を補うことができます。
都市によって生活スタイルや物価も異なり、選び方次第でコストコントロールが可能です。
| 都市 | 特徴 | 月額費用の目安(授業+生活費) |
|---|---|---|
| オークランド | 最大都市で学校数も多く、利便性が高い | 約14〜16万円 |
| クライストチャーチ | 落ち着いた地方都市。物価がやや安め | 約12〜15万円 |
| ウェリントン | 首都で文化・政治の中心。暮らしやすい | 約13〜15万円 |
年間での費用は160万〜190万円前後が目安で、落ち着いた生活環境を重視したい人や、英語初心者にもやさしい国として支持されています。
このように、費用対効果の高い国を選ぶことで、年間数十万円単位の節約も可能になります。
単に「安さ」だけでなく、「どんな英語環境で学びたいか」「現地での生活スタイルはどうか」など、自分の目的に合った国を選ぶことがポイントです。
※本文中の費用目安は、2025年5月時点の参考為替(例:1米ドル ≒ 150円、1カナダドル ≒ 114円、1オーストラリアドル ≒ 102円、1フィリピンペソ ≒ 2.7円)を基準に算出しています。
為替の変動によって実際の費用は変動する場合があります。
現地での節約アイデアと生活の工夫

語学留学中の費用は、渡航前の準備や学費だけでなく、現地での生活コストによっても大きく変わります。
現地での過ごし方次第で、月に数万円、1年で数十万円の差が生まれることも。ここでは、実際に効果のある節約アイデアと工夫を紹介します。
自炊+日本の味を上手に取り入れる食費節約術
外食中心の生活は出費がかさみやすく、特にオーストラリアやニュージーランドなど物価の高い国では、1食で1,500〜2,000円近くかかることも。
自炊を習慣化することで、月の食費を1〜2万円以上節約できます。
炊き込みご飯・パスタ・炒飯・具なし味噌汁などは、食材が少なくて済む優秀メニュー。
現地スーパーの特売や冷凍野菜を活用することで、自炊のハードルはかなり下がります。
アジア系スーパーを利用すれば、日本食の再現も可能です。
ただし、しょうゆやみそなどの調味料はローカルスーパーよりやや割高な傾向があるため、用途を絞って使うのがコツ。
外食よりは安く、"食べたいときに作れる安心感"が強みです。
また、最初の1か月程度に限り、日本から即席ご飯やレトルト食品を持参するのも有効です。
以下のようなスタイルで準備する人が多いです:
パックご飯・インスタント味噌汁・レトルトカレー・お茶漬けの素などを10〜15食分ほど
電子レンジがある滞在先であれば、簡単に食事が取れる
日本食が恋しくなる初期の心の安定剤としても効果的
※肉類を含む食品は、入国制限のある国もあるため事前に持ち込みルールを要確認しましょう。
交通費は定期券やシェアバイクを活用
都市部では意外と負担になるのが交通費。学生割引の定期券がある地域では、到着後すぐに申し込むのがおすすめです。
たとえば、カナダ(トロント・バンクーバー)やニュージーランド、マレーシアでは、学生ビザ+学生証の提示で公共交通機関の学割カードや割引定期券が利用可能です。
マルタでも長期滞在者向けの学生プランがあり、定額制で交通費を抑えられます。
また、オーストラリアの一部都市やニュージーランドでは、自転車のシェアサービスや月額サブスクも活用でき、通学コストを大幅にカットすることが可能です。
ルームシェアで住居費を調整:探し方と注意点
住居費は固定費の中でも大きな出費です。ホームステイや学生寮から、現地でルームシェアに切り替えることで、月3万〜5万円の節約になるケースもあります。
ルームシェア物件の探し方は国によって異なります。
たとえば:
オーストラリアでは、
Gumtree:生活全般の掲示板サイト
Flatmates.com.au:ルームシェア専門検索サイト
ニュージーランドでは、
Trade Me Property:最大の不動産サイト
Facebook Marketplace や日本人コミュニティグループ
他にも、語学学校の掲示板、エージェント経由の紹介、知人のつてなど、複数のルートを併用して探すのが賢明です。
契約時の注意点:
敷金(bond)や前家賃は、1〜4週間分が相場(両国共通)
オーストラリアでは法律で最大4週間までと規定
ニュージーランドではTenancy Servicesへの登録が義務(正式契約時)
礼金の文化は基本的にありません
契約内容は英語なので、退去時の条件・光熱費の取り決め・家具付きかどうかなどを事前に確認
ルームメイトとの相性や生活ルールも重要。可能であれば内見や面談の場を持つと安心です
また、家賃を抑えるために郊外を選ぶ人も多いですが、その分通学の交通費や治安とのバランスも考慮する必要があります。
無料アクティビティを活用して交際費を抑える
語学学校や地域コミュニティでは、無料の交流イベントやアクティビティ(BBQ・ハイキング・会話クラブなど)が定期的に開催されています。
こうした場を活用すれば、交際費をかけずに友人を増やし、英語を使う機会も増やせます。
不用品は買わずに「借りる/譲ってもらう」
現地生活で必要になる家具や生活用品は、現地の掲示板やSNSグループで「無料譲渡」や「格安販売」が見つかることも。とくに長期滞在者が帰国するタイミングは狙い目です。
これらの工夫を組み合わせることで、月あたり3万〜6万円、年間で30万〜50万円以上の節約も十分可能です。
現地で慣れてくると、自然と自分なりの節約術も見つかるはず。楽しみながら、無理のないやりくりを心がけましょう。
奨学金・ワーホリ・現地バイトの活用

語学留学の費用を少しでも軽減するためには、「払う」だけでなく、収入につながる制度や支援を活用する視点も大切です。
ここでは、留学コストを補うために知っておきたい主な3つの方法を紹介します。
日本の奨学金制度を活用する
「語学留学は奨学金の対象外」と思われがちですが、実は語学目的でも応募できる奨学金制度は存在します。
たとえば:
JASSO(日本学生支援機構)の海外留学支援制度(短期派遣)
→ 大学に在籍していることが条件。提携先を通じて応募地方自治体・民間団体の独自支援(例:ロータリー財団、トビタテ!留学JAPAN)
→ 語学だけでなく「何を目的に留学するか」が問われる傾向
いずれも応募時期や条件が限られているため、半年〜1年前からの情報収集が鍵になります。
また、最近は「社会人向け」「高専生・専門学校生向け」など、対象を広げた制度も増えてきており、探せばチャンスはあります。
ワーキングホリデーで働きながら学ぶ
18〜30歳(国によっては35歳まで)が対象のワーキングホリデー(通称:ワーホリ)は、語学留学と就労体験を組み合わせたい人にとって有力な選択肢です。
カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなどが特に人気
ワーホリビザでは、就学と就労の両方が可能(国により就学期間に上限あり)
飲食店・カフェ・ホテルなどでのアルバイトをしながら生活費を補える
「働きながら学べる」唯一のビザであり、費用の自己負担を減らしながら長期滞在できるのが魅力です。
語学力初級でも受け入れてくれる職場もあり、現地での実践的な英語力を伸ばす場にもなります。
学生ビザでもアルバイトできる国を選ぶ
ワーホリに該当しない人でも、学生ビザで就労が認められている国を選べば、現地での収入を得ることが可能です。
| 国 | 学生ビザでの就労可否 | 条件 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 可能(2週で48時間まで) | 学校に在籍している間のみ |
| ニュージーランド | 可能(週20時間まで) | 語学学校が認可校であること |
| カナダ | 条件付きで可能 | 公立カレッジなど就学機関により異なる |
| マルタ・マレーシア | 一部可/不可 | ビザの種類・滞在期間・学校の認可状況による |
たとえば、マルタでは「90日以上の学生ビザ」で、政府認定校に在籍している場合に限り、週20時間までの就労が可能です。
ただし、ビザ申請後60日以上経過してからでないと働けないなど、手続きとタイミングに制限があります。
マレーシアは原則として学生ビザでの就労は不可ですが、長期留学者や大学付属機関に在籍している場合、申請制で一部の就労(キャンパス内など)が認められるケースもあります。
いずれもハードルはやや高めなので、事前に大使館や学校を通じて確認することが重要です。
就労可能な国では、授業後や週末の時間を使って、飲食・販売・清掃などの軽作業で時給1,000円前後を稼ぐこともできます。
とはいえ、語学力や地域、求人状況により左右されるため、「確実に稼げる」とは思わず、生活費の一部補填程度に考えるのが現実的です。
これらの制度や選択肢を組み合わせることで、語学留学の総コストを大きく下げることが可能になります。
奨学金・助成制度の活用ステップ

語学留学の費用を支援してくれる奨学金や助成制度は、探しにくそうに見えても、実は語学目的でも応募可能な制度は存在します。
ここでは、実際に使える制度の具体例を紹介しながら、活用までの流れを詳しく説明します。
ステップ①:語学留学でも対象になる制度を知る
奨学金と聞くと「大学正規留学や研究目的向け」というイメージが強いかもしれませんが、語学留学にも対応している制度もあります。代表的な例は以下の通りです:
【大学生対象】
🔹JASSO(日本学生支援機構)海外留学支援制度(協定派遣型)
- 大学間協定に基づく派遣留学に限り、月額6〜12万円の給付+渡航費支給
- 事前に在籍大学の国際課を通じて申し込みが必要
- 語学目的でも「学習成果が期待できる内容」であれば対象になり得る
【高校生対象】
🔹トビタテ!留学JAPAN(高校生コース)
- 高校在学中に最大6か月の海外留学を支援
- 旅費・滞在費に加え、留学準備金も支給(最大50万円超)
- 文部科学省と民間企業の共同支援で、語学・ボランティア・スポーツなど幅広く対応
【社会人対象】
🔹ロータリー財団 グローバル補助金奨学金
- 地域ロータリークラブの推薦が必要
- 大学院留学が主流だが、英語力強化や文化交流を目的とした短期留学支援も対応例あり
- 国際平和・地域発展などのテーマとの関連性があると有利
ステップ②:募集時期・条件をしっかり把握する
これらの奨学金は年に1回〜2回の募集で、かなり早い段階から準備が必要です。
特にJASSOやトビタテ!は出願締切が出発の約半年前〜1年前に設定されており、語学学校の選定・ビザ取得のタイミングと合わせて動く必要があります。
トビタテ!高校生:毎年秋ごろに翌年出発分の募集開始
JASSO協定派遣:大学ごとに推薦締切が異なる(年1回が基本)
【ポイント】条件に「語学力証明(英検・TOEFLなど)」が含まれるケースもあるため、早期の英語学習開始が有利です。
ステップ③:所属機関・地域の制度もチェック
所属する大学や高校が独自に留学支援金を設けていることもあります。特に私立大学では、年間5〜10万円程度の「短期海外研修奨学金」などが提供されていることも。
また、以下のような自治体レベルの助成も存在します:
【例:東京都世田谷区】「海外派遣助成金」
→ 高校生対象、語学研修に上限20万円の補助あり
【例:神奈川県大和市】
→ 語学留学中の若者に、一律10万円の助成金支給
地元の広報誌や教育委員会HP、社会福祉協議会などで定期的に情報を確認すると、思わぬチャンスを見つけられることがあります。
ステップ④:応募書類と志望理由の質がカギ
ほとんどの奨学金では、単なる申請だけでなく「なぜ自分が支援を受けるべきか」を説明する文章(志望理由書)が必要です。
目的と計画が具体的か?(例:帰国後の活用、学習目標)
なぜその国・学校なのか?
費用がどのように必要なのか? 他に収入源はあるのか?
💡 採用担当者は「投資に値する人か」を見ているため、社会的意義・再現性のある計画を示せると評価されやすいです。
ステップ⑤:採用後の義務と使い道を確認
奨学金によっては、定期レポート提出・現地活動の報告書提出などの義務がある場合があります。
また、「学費にのみ使用可」「生活費への使用は一部制限あり」などのルールがあることも。受給後にトラブルにならないよう、利用規約を丁寧に読み込んでおくことが重要です。
奨学金の活用は、「探す手間がかかる」「難しそう」と感じるかもしれませんが、準備が早い人ほど選択肢は確実に広がります。
語学留学=自己負担だけで行くもの、という常識にとらわれず、制度を味方につけて留学のチャンスをつかみましょう。
実例紹介:節約留学を成功させた人の工夫

語学留学は高額なイメージがありますが、情報収集と工夫次第で予算を抑えながら充実した留学生活を実現することは可能です。
ここでは、実際に節約型の留学を成功させた2人の事例を紹介します。
ケース①:大学2年・美咲さん(20歳)|フィリピン・セブ島でのマンツーマン集中留学
目的:就職前に英語面接対策&TOEICスコアUP
期間:8か月
学校:セブ市内のマンツーマン特化型語学学校
滞在:学生寮(3人部屋、食事付き)
費用感:総額約105万円(授業料・寮・航空券・保険含む)
工夫したポイント:
出発5か月前からリサーチし、複数校のキャンペーンを比較して授業料を約20万円カット
シーズンオフを狙って航空券を早期予約(往復約6万円)
学校主催の無料アクティビティを活用して交際費を削減
渡航前に日本から即席ご飯・みそ汁などを30食分持参し、外食をほとんどしなかった
コメント:
「留学ってもっと高いと思ってたけど、先に調べて動けば案外なんとかなるんだと実感。TOEICも200点アップして、就活にも自信がつきました!」
ケース②:社会人・雄大さん(26歳)|マルタでの長期語学+リモート勤務の両立
目的:英語スキル維持と海外生活への挑戦
期間:12か月
学校:セントジュリアンの私立語学学校(週20時間コース)
滞在:シェアアパート(日本人2名とルームシェア)
費用感:実質支出 約130万円(現地収入と併用)
工夫したポイント:
渡航前に勤務先と調整し、週3リモート勤務と学習を両立
住居はFacebookの現地グループで見つけた月家賃約4万円の物件
食費は現地スーパー+週1マーケットで節約、ほぼ毎日自炊
徒歩圏内の語学学校を選んで交通費ゼロ、娯楽は無料イベント中心
コメント:
「“海外に行く=全額自費で通学”と思ってたけど、働き方を調整すれば、意外とリアルに実現できる。英語も仕事も同時に成長できて、大正解でした。」
このように、自分の目的に合ったスタイルと工夫をかけ合わせることで、節約型でも十分満足度の高い留学が可能です。
まずは「どんな留学がしたいか」と「自分に何ができるか」を照らし合わせて、現実的な選択肢を探してみましょう。
最後に:行かない理由ではなく、「行ける方法」を考えてみよう
留学は簡単な挑戦ではありません。費用も時間も勇気も必要です。
でも、行かない理由を見つけるのは、誰にでもできること。
「お金がない」「語学力がない」「タイミングじゃない」
そんなふうに、自分を納得させるのはたやすい。
けれど本当に大事なのは――
「どうすれば行けるようになるか?」と自分に問い直してみることです。
一歩踏み出す勇気があれば、見える景色は確実に変わります。
しかもその一歩は、“今”しか踏み出せないかもしれないのです。
若いときにはなかなか想像がつかないかもしれませんが、
人生は、思っているより短く、チャンスの数も有限です。
やれるときにやらなかったことは、
実は多くの人が人生の最後に強く後悔することのひとつでもあります。
完璧な条件がそろうのを待つ必要はありません。
限られた条件の中でも、自分なりにできる留学を形にしてみること。
その挑戦が、あなたの未来をきっと変えてくれます。
記事まとめ:コストを抑えて1年間の語学留学を実現する方法
- 留学費用は国・都市・滞在スタイルにより大きく異なる
- フィリピンやマレーシアは授業料・生活費ともに抑えやすい
- マルタやニュージーランドもコスパ重視層に人気の留学先
- 都市ごとの生活コストや物価差を事前に把握することが重要
- 食費は外食を避けて自炊中心にすることで大幅に節約できる
- 即席ご飯や日本食を初期に持参する工夫で外食回数を減らせる
- 滞在費はホームステイや寮からルームシェアに切り替えると効果的
- オーストラリアやNZではFacebookやローカルサイトで部屋探しが主流
- 学割定期券やシェアバイクの活用で交通費を抑えることが可能
- 留学中の交際費は無料アクティビティやイベントで節約できる
- 不用品は買わずに現地コミュニティで借りる・譲ってもらう選択肢もある
- 奨学金制度はJASSOやトビタテなど語学目的でも応募可能なものがある
- 自治体や学校独自の助成制度も意外と多く見落とされがち
- ワーホリや学生ビザで働ける国を選べば現地収入の補填ができる
- 節約型留学でも満足度は高く実現可能であることが実例からわかる
- 留学は完璧な条件を待つものではなく、行ける方法を考えることで道が開ける